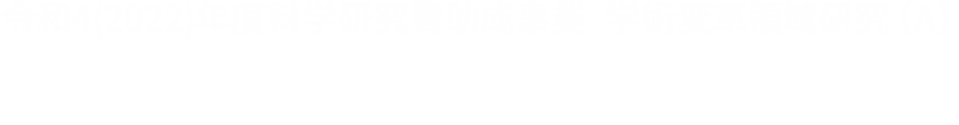研究概要
本領域研究は、日本における「「貧困」の研究」を学術領域として確立し、貧困政策のエビデンスに基づく立案(EBPM)の要となる研究者集団を育成することを目的としています。
本領域研究では,貧困研究を「貧困学」という融合学術として確立するとともに,政策科学として、その成果を行政および貧困の現場(教育、医療、福祉など)とのフィードバックの中で飛躍させることを目指します。そのために、一つのデータセットを共同利用し、異なる視点・異なる分析手法で分析するデータ・ドリブン(data driven)な手法を採用します。具体的には,全国300以上の自治体が行っている子どもの貧困調査を統合しビッグデータのデータベースを構築します。このデータの構築過程では、学際的に協議を重ね、共同利用することを通して、共通の言語で貧困を語ることができる研究者コミュニティを形成していきます。
さらに,本領域研究のもう一つの目的は、分析から得られた結果を政策的に実装するために、データ提供者である自治体に還元し、貧困研究を貧困政策のEBPMに位置付けることです。研究成果を政策に実装するには、それを後押しする世論の形成、政治における駆け引き、財源の確保、行政的ハードル(制約)の解消が不可欠です。そのため,行政学・財政学・政治学などの専門家を集めて研究成果の実装のためのプログラム開発およびフィージビリティを検討するチームを設置しています。
なお、本領域研究では、データベースの内容上、子どもを対象とした研究が中心になりますが、貧困学はもちろん年齢に関係なく広く扱うべき課題です。しかし、残念ながら現時点の日本においては大人の貧困については自己責任論が根強く、政策どころか調査の必要性も社会的に認知されていません。逆に考えれば、子どもの貧困に注目が集まっている今こそ、子どもの貧困学の発展を突破口として、貧困学を発展させる必要があります。